71回 故・清水勲氏は、1983年には労働組合の委員長だった
小野耕世『長編マンガの先駆者たち――田河水泡から手塚治虫まで』(岩波書店、2017年)と手塚治虫の話は、70回で記した。
小野耕世『長編マンガの先駆者たち』の刊行を記念して、親しくしていた銀座の若山美術館で、「小野耕世、マンガづけの少年時代」展という展覧会(2017年4月25日‐6月24日)を開催し、小野耕世氏と私の対談(実際は、小野耕世独演会)というイベントも2回行なったのだが、清水勲氏も、このイベントに来場してくれた。

清水氏にお会いしたのは、ずいぶん久しぶりだったが、イベント後、銀座の街角でお仲間たちに囲まれているのを遠くから見たときも、かつての陽気な清水さんのイメージではなく、とても静かな様子だった(清水氏が亡くなったのは2021年のことだが、このころから、体調がすぐれなかったのだろうか)。
その後、『東京新聞』(2017年7月30日)に、清水氏による書評が掲載された。
「著者は私と同じ昭和十四(一九三九)年生まれで共に東京育ち。少年期の長編マンガ読書体験をもとに、作品のマンガ史的意味と作家に対する思い入れを語っている.。とくに著者が昭和二十年代前半における長編子どもマンガのリアルタイム読者であったことは、戦後マンガ創成期の複雑な実像を若い世代に伝える意味を持っている」と、この本の特徴をとらえて書き始めている。編集した私としても、「その通りなんですよ!」と、大きくうなずいてしまう文章だ。
ところが後半では、「本書でちょっとわかりにくいのは、「長編子どもマンガ」と「長編大衆マンガ」の流れである」と注文をつけている。じつは、この清水氏の後半の文章こそ、「ちょっとわかりにくい」のである。

文章は、以下のように続く。
「前者のスタートは大正六(一九一七)年、岡本一平が児童雑誌『良友』に連載した「珍助絵物語」。それを継いだのが、弟子の宮尾しげを(「団子串助漫遊記」など)であり、「のらくろ」に代表される講談社マンガ、「火星」に代表されるナカムラマンガである。「長編大衆マンガ」は大正七年の近藤浩一路「漫画坊っちゃん」(新潮社)からスタート、岡本一平「人の一生」(『婦女界』大正十三~昭和四年連載)を経て、「現代連続漫画全集」につながる」。
このように清水氏が記す「「長編子どもマンガ」と「長編大衆マンガ」の流れ」は、『東京新聞』の読者(私もその一人)に、簡単には通じないと思えたし、清水氏による漫画の歴史の読みかたが、すべての人に共通の常識として定着しているはずもないと思った。それに、この本で小野耕世氏がナカムラ・マンガ・シリーズなどに触れたのは、「日本の長編ストーリーマンガ発展の〈起爆点〉は、一九三〇年代ではなかったか」という、以前からの小野氏の思いを掘りさげた「序章」においてのことで、もとより体系的・系統的な構成の記述を目指したものではない。そもそも、小野氏の文章の魅力は、少年時代を回想するときのみずみずしい感覚にあり、彼が、論理よりも感性・感覚の人であることは、清水氏ならば、よく知っていたはずだ。
この書評を読み、展覧会を開催してくれた若山美術館の武田文館長の、「清水さん、どうしちゃったんだろうね」という声を聴きながら、私は数十年前に日本リーダーズダイジェスト社労働組合の異色委員長として清水氏が紹介されていた記事を思い出していた。

記事の中で、「残りの人生を十億秒として、好きなことができるのはせいぜいあと三億秒」と答えていた清水氏は、その後、約十一億九千秒を生きたことになる。次回以降、清水勲氏の思い出や、彼が構築した日本の漫画史について考えていきたい。
70回 手塚治虫の初期4コママンガ「女、ゆるすべからず」掲載の『ユーモア』(春陽堂)
小野耕世『長編マンガの先駆者たち――田河水泡から手塚治虫まで』(岩波書店、2017年)を編集したとき、若き手塚治虫が影響を受けたマンガとして、『アサヒグラフ』『東京朝日新聞』に翻訳連載されたジョージ・マクマナス「親爺教育」「おやぢ教育」を調べたことがある。
もともとアメリカでは平日の新聞に載っていた4コマ版の「親爺教育」は、1923(大正12)年の関東大震災前に日刊『アサヒグラフ』(活版印刷)に連載され、震災後には『東京朝日新聞』に連載された。アメリカの日曜版に1ページを占めて掲載された12コマ版は、震災後に再創刊された週刊『アサヒグラフ』(グラビア印刷)に、「おやぢ教育」の名で連載された。「おやぢ教育」の掲載は、1923年11月14日創刊号から1940(昭和15)年7月31日号までで、手塚治虫が影響を受けたのは、この週刊『アサヒグラフ』の連載である。
誤解のないように記しておくと、手塚治虫がジョージ・マクマナスの「おやぢ教育(ジグスとマギー)」の絵柄を模写して使ったことは、秘密ではなく、手塚自身が話していることである。
「ジョージ・マクマナスという人はもともとはマンガ家じゃなくて、建築設計士だったんですね。ですから、ビルのたたずまいだとか、部屋の中のインテリアだとか、たいへんすばらしい。最先端のニューヨークの情景が描けるわけですよ。それを見て、ぼくはニューヨークにあこがれ、アメリカ文明や、機械文明にあこがれたわけだけれど、それだけではなくて、ぼくの「鉄腕アトム」以前のSFマンガの、とくに背景っていうのは「ジグスとマギー」そのままといっていいくらい、影響を受けましたね」(『手塚治虫漫画全集別巻 手塚治虫漫画の奥義』聞き手:石子順、講談社、1997年)


手塚治虫が「ふしぎ旅行記」(家村文翫堂、1950年)に模写して使っていたことを、小野耕世氏が発見した「おやぢ教育」(『アサヒグラフ』1938年6月15日号)

旅行記」(家村文翫堂、1950年)の最終節「動物園異変」の
1ページ(復刻版、角川書店、2001年)
週刊『アサヒグラフ』の「おやぢ教育」には「連載第◯回」という表示はないが、今回の文章のなかで掲載回数を示したいというのが、小野耕世氏の考えだった。「おやぢ教育」の連載第1回と最終回はわかっているが、飛び飛びに掲載されていない号があり、巻数号数の引き算だけでは、掲載回数を割り出すことはできない。私の手元にある『アサヒグラフ』には欠号が多い。
こういうときは、朝日新聞記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」で検索するに限る。ところが検索しても、週刊『アサヒグラフ』連載の「おやぢ教育」の、1937(昭和12)年から1940年が出てくるだけである。日刊『アサヒグラフ』連載の「親爺教育」(1923年)と、週刊『アサヒグラフ』連載の「おやぢ教育」の1936(昭和11)年までの分は、マンガ名や著者名で検索しても引っかかってこない。画像を見ると明らかに掲載されているのに、各号の目次にも取り上げられていない。
1か所、作品名の間違いも発見したので、ついでに朝日新聞社に問い合わせたところ、以下のような返事をいただいた。
「アサヒグラフの「目次・概要」は目次があるときは目次を、「目次」がない場合は、「概要」という形で、内容を抜粋して拾っています。1937年からはアサヒグラフに目次が付いているので、目次をそのまま入力しています。1936年まではアサヒグラフに目次が付いていない時期があり、目次の代わりに内容をピックアップした「概要」を入力しています。「概要」は、グラフ誌という性質上、「ニュース写真」「風俗写真」など写真を優先的に拾っています。1936年までの「おやぢ教育」が検索できないのは、「概要」として拾っていないためです。」
「聞蔵Ⅱビジュアル」に拾われていない13年間の号を、すべて画面で見て確認するには何日もかかるし、数え間違いをしてしまいそうに思えた。そこで、正確な数字は別の機会にゆずることとして、小野耕世『長編マンガの先駆者たち』では、週刊『アサヒグラフ』に連載された「おやぢ教育」についての記述を、「足かけ十八年、八百回を優に超えるエピソードで、日本の読者を楽しませた」と無難な表現にしてもらったのだった。
このとき、「聞蔵Ⅱビジュアル」を検索して得られた教訓は、人がひとつひとつ入力して、データベースを構築しているという事実で、だから、目次に記載されていない記事がデータベースに拾われる可能性はとても少ない、ということだった。
『長編マンガの先駆者たち』刊行から3年も経って、そんなことを思い出したのは、2020年4月に『手塚治虫アーリーワークス』(888ブックス)が刊行されていたことに、8月下旬になってから気がついたからだ。
ネットで内容を確認したところ、4コママンガ「女、ゆるすべからず」が収録されているが、発表年は不明となっている。また、手塚治虫公式サイト「虫ん坊」の「手塚治虫の原点にさかのぼれ!「手塚治虫アーリーワークス」制作チームインタビュー」によると、今回の作品集の中心は、「手塚先生が自ら新聞掲載作品を集めたスクラップブック」から作製されたという。
じつは、「女、ゆるすべからず」は、春陽堂の『ユーモア』1948(昭和23)年2月号(第12巻第2号)の29ページに掲載されている。手塚治虫が19歳のときの作品だが、マンガの左に縦書きで「女、ゆるすべからず(手塚治画)」と、作品名と本名が記されるだけで、目次には、なにも掲載されていないのである。


『ユーモア』の前身は戦前の『ユーモアクラブ』で、『明朗』を経て『ユーモア』になったようだが、あまりみかけない雑誌で、国立国会図書館でも、プランゲ文庫のマイクロフィッシュ以外は1947(昭和22)年3月号のみ所蔵のようだ。プランゲ文庫のデータベースとして、NPO法人インテリジェンス研究所が作成した「20世紀メディア情報データベース」が有料で公開されているが、基本は目次入力であるらしい。はたして、手塚治「女、ゆるすべからず」は入力されているだろうか。
私が持っている『ユーモア』は、1948年2月号(第12巻第2号)と5月号(第12巻第5号)。表紙絵はどちらも生沢朗で、5月号では、国会議事堂とバラック住居、英文道路標識によって、1948年の東京を鮮やかに記録している。

69回 戦後の『月刊読売』の製本方式と娯楽性(3)

『月刊読売』の編集者は、1947年の表紙絵に岩田専太郎を4回起用し、本文挿絵にも毎号のように登場させていたが、「中味」の大幅刷新を、1947年12月号(第5巻第12号)から始める。まず、平綴じ製本の特性を生かして、巻頭にオフセット印刷の口絵4ページを新設し、南義郎・田中比左良・小野佐世男・杉浦幸雄という4人の人気漫画家を登場させて、大衆娯楽路線を鮮明にする(本文40ページが普通だったが、この号は48ページ)。
平綴じ製本では、口絵ページを入れる場所は、折り丁の境目であれば可能だから、4ページの口絵を巻頭に入れるのは容易なことだ。読者が表紙をめくれば、すぐに口絵が目に入り、実際以上に豪華に見える(中綴じ製本では、前半部分と後半部分が対称になるので、巻頭に4ページの口絵ページを構成するには、巻末分と合わせて8ページ分の製版・印刷が必要となり、ページ数の少ない時代にはむずかしい)。

1948年6月号(第6巻第6号)を見ると、巻頭の4ページは4色印刷(1ページ目の「目次」では黄版を使わずに製版しているようだ)で、「夏姿女三代」を、岩田専太郎、林唯一、高井貞二に依頼している。残りの4ページは藍版抜きの3色印刷で、小川哲男、小野佐世男、杉浦幸雄に「お好み色刷漫画 当世裸時代」を描かせている。口絵の最終ページ(8ページ)は、残念なことに広告になっているが、色刷りページの広告は、それなりの収入を見込めそうだ(坂口安吾や田中英光も服用したという「熟眠剤アドルム錠」の広告に注目!)。そして、9ページから始まる活版印刷の本文では、木々高太郎「死の設計図」の挿絵に富永謙太郎を起用する。『月刊読売』が打ち出した大衆娯楽路線は、人気者をずらりと並べるにぎやかなものだ。
68回 戦後の『月刊読売』の製本方式と娯楽性(2)
1946(昭和21)年1月に復刊した『月刊読売』が中綴じ製本だったのは、ごく短い期間で、手元の号で見ると、1946年5月号(第4巻第6号)から平綴じ製本になっているが、これは、「簡易平綴じ製本」とでも呼ぶべきものだ。本来の平綴じは、本体を綴じたあとに表紙をつけて、製本の針金を表紙で隠すが、5月号の針金は表紙の上から打たれている。そして、本文は中綴じ用の面付けになっていて、活版印刷32ページ1台の中央に単色グラビア4ページが綴じ込まれている。つまり、前回取りあげた復刊号(第4巻第1号)と構成は同じなのだが、針金の打ちかたが違う。中綴じではなく平綴じとして針金を打ち、外観だけの平綴じ製本としているのである。中央のグラビアページ(89歳の尾崎行雄を熱海の惜檪荘――岩波茂雄の別荘である――に訪ねた「尾崎さん元気でゐてください」という記事)は、復刊号とは逆に、中綴じ用にノド一杯まで使ったレイアウトになっているのに、平綴じの針金のおかげでノドまで開かず、無理にのぞきこまないと、文字が読めない。ちなみに、前回紹介した通り、2月号では巻頭は1ページと数えたが、この5月号の本文は巻頭を3ページと数えていて、1946年7月15日発行の「夏の増刊号」(第4巻第9号)で戦後の標準形(1ページから数える)に統一されるまで、一進一退である。
写真ページは諧調に優れたグラビア印刷が一番、というのが長年の常識で、『月刊読売』でも、前年までは口絵にグラビア印刷を使っていた。しかし、グラビア印刷による口絵は、堅苦しすぎると考えたのか、1947年の号には見当たらない。本ブログ「66回 『青年読売』の最終号は、1945年4月1日発行の「第4輯」(2)」で触れたように、1946年の「夏の増刊号」から、印刷所を読売新聞社に替えたことで、グラビア印刷が手配できなくなったのかもしれない。


67回 戦後の『月刊読売』の製本方式と娯楽性(1)
さて、『月刊読売』の戦後復刊(1946年1月)以降の製本方式と娯楽性との関連、それに連動するページの数えかたの変遷について、簡単に俯瞰しておきたい。
戦後の『月刊読売』の歩みは、刊行頻度を上げて、先行する週刊誌『週刊朝日』『サンデー毎日』に追いついていく歴史と言ってよい。1951(昭和26)年4月1日には、「月刊」の名のままで半月刊(月2回刊)となり、1951(昭和26)年11月1日号から『旬刊読売』、1952(昭和27)年7月13日号から『週刊読売』と改題される。『週刊朝日』『サンデー毎日』の対抗馬としての『週刊読売』を、新聞社系週刊誌のなかでは戦記物に強かったな、と記憶している読者は、その前身の『月刊読売』時代も、新聞社系の雑誌として時事情報中心に歩んできたと思い込みがちだ。

戦争末期の『青年読売』休刊号(第3巻第4号)と同様に、中綴じ製本で刊行された『月刊読売』1946(昭和21)年1月復刊号(第4巻第1号)は、1945(昭和20)年12月18日の『読売報知』で、「廿日発売一月号八十銭」と予告された。巻頭に口絵はなく、「巻頭言 新らしき出発」と「目次」が掲載されたページから始まっている(このページの画像は、前回の本ブログに掲載したが、ノンブルは「5」と振られている)。
そして、中綴じ製本中央の20ページと21ページの間に、ひと目で平綴じ用レイアウトとわかる(ノドに、針金綴じのための約9ミリ幅の余白をつけている)グラビア4ページ分が綴じられて、針金が1か所見えている。20ページから始まる記事は、上3段分が鈴木茂三郎「財閥と青年」、下2段分が中川善之助「婦選の良心」で、20~21ページの見開きでレイアウトされている。その見開き記事に割り込む形で、グラビア4ページが挿入されているのだから、いかにも不自然だし、読みにくい。戦中と同様の平綴じを予定し、グラビアは巻頭口絵として準備されていたのが、何らかの手違いで、本文は中綴じ用に面付けされて刷了になり、中綴じ製本のラインに送られたのであろう(表紙は、背幅のある平綴じ用にレイアウトされて、背文字が入れられている)。



さて、『月刊読売』1946年1月復刊号は、間違って中綴じ製本ラインに送られてきたと気がついた時点で、本来の平綴じ製本のラインに回し、体裁は少々悪くても、本文32ページ1台の前に口絵をつけて平綴じの体裁にすることは、技術的には可能だったはずだ。しかし大日本印刷には、1946年1月号からスタートする雑誌の仕事が次々に持ち込まれ、スケジュールが満杯になっていたに違いない。規模が大きい分、小回りが利かない。発売日を遅らせずに刊行する解決策は、このように口絵を中央に綴じてしまう、というものだった(石川巧『「月刊読売」解題・詳細総目次・執筆者索引 増補改訂版』三人社、2014年は、この4ページ分を「付録」として処理している)。
66回 『青年読売』の最終号は、1945年4月1日発行の「第4輯」(2)
週刊誌であれば、表紙(表紙1)を1ページ、表紙裏(表紙2)を2ページと数え、本文は3ページから始まるのが普通だが、『青年読売』は『月刊読売』時代から、他誌とは違う数えかたをしていて、通常の週刊誌と比べ、ページ番号(ノンブル)が2ページずれている。本号の本文最終ページのノンブルは「三六」となっているが、枚数を数えると、本文は32ページで、表紙・裏表紙を合わせて36ページである。ほかの号に当たってみても、どうも、表紙から裏表紙(表紙1~表紙4)を先に1~4ページと数え、本文を5ページから数え始めているらしい(戦後まもなく、表紙を数えずに、本文の巻頭から1ページと数えるようになり、そののちには、通常の週刊誌と同様の方式になる)。

本号の表紙には、襟章(陸軍上等兵か)をつけた兵士が突進しようとする姿に、「一億斬込み!」という標語が入れられている。本文にも「我に斬込戦法あり」という記事が載っているが、この表紙の兵士の肩から背中にかけて見える偽装用ネットや破れた衣服から、目前に迫ってきた「本土決戦」の厳しさが伝わってくるようだ。


手元の資料では、『月刊読売』復刊号の次に『青年読売』の名が出てくるのは、『日本出版年鑑 昭和19.20.21年版』(日本出版協同、1947年)だ。「雑誌部門別三年史」の「綜合・時局」の項(1946年時点での記述になっている)では、「「放送」「青年読売」の二誌は昨年初頭空襲の激化により印刷能力を失つて休刊し、本年に入つて再刊した」と記され、「初頭」以上に細かい休刊時期を示していない。
そして、『日本出版年鑑 昭和19.20.21年版』の記述を22年後になぞったものと思われるのが、『日本雑誌協会史 第二部』(日本雑誌協会、1969年)で、「「放送」と「青年読売」は空襲で印刷できなくなり休刊した」と記されている。「空襲の激化により印刷能力を失つて休刊」と、「空襲で印刷できなくなり休刊」とでは、微妙に異なる表現ではあるが、果たしてどのような状況だったのか。1945年の印刷所に目を向けて考察してみよう。
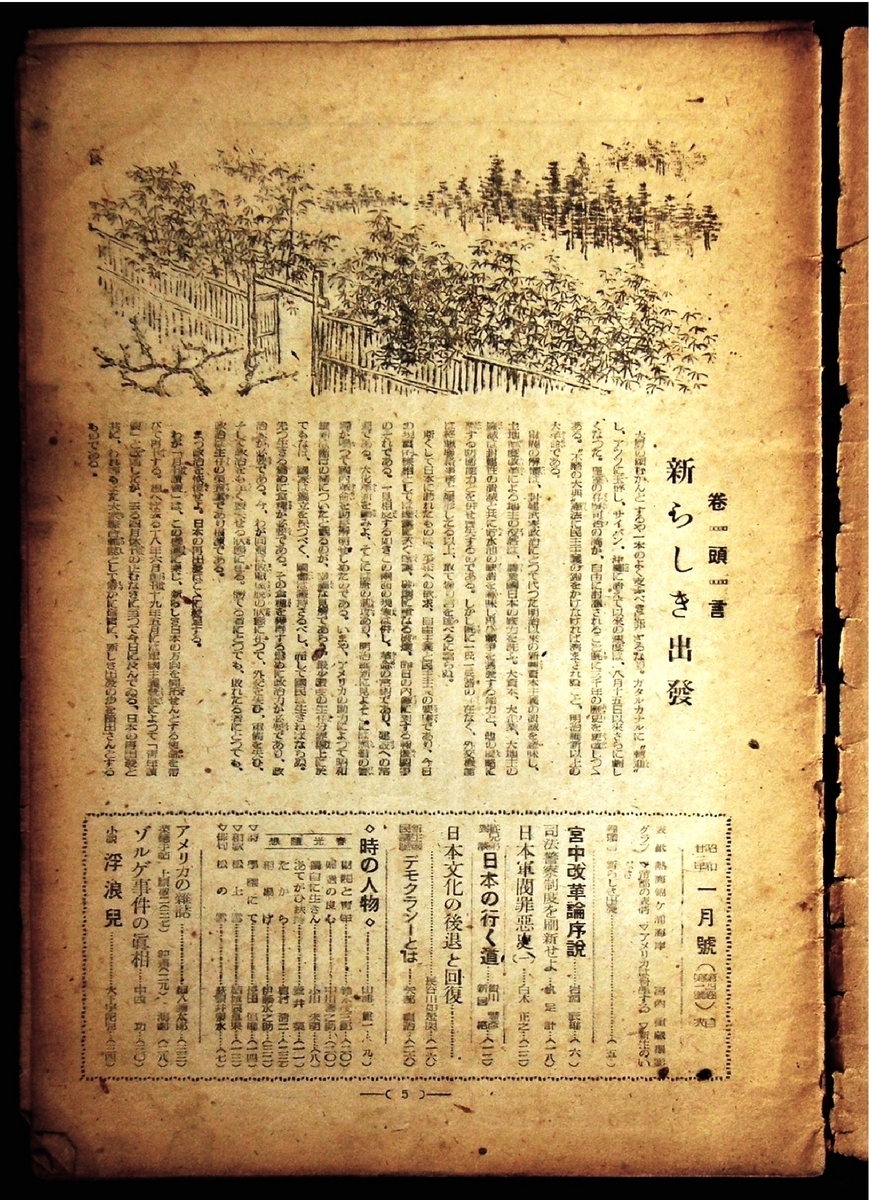

本ブログの「49回 3月10日の東京大空襲(1)」で『写真科学』と『講談倶楽部』が空襲によって欠号したり合併号を出したことを紹介した。『写真科学』の1945年1-2月合併号までの印刷所は、小石川区久堅町108番地の共同印刷だったのが、戦前最終号の1945年5-6月合併号では、神田区錦町3丁目1番地の大同印刷になっている。また『講談倶楽部』の印刷所は、かつては麹町区丸ノ内3丁目8番地の有恒社だったのが、1944年には小石川区東古川町10番地の中外印刷になっている。
大日本印刷は、『大日本印刷百三十年史(資料編)』(大日本印刷、2007年)の年表中、1945年の項に「5.25 空襲により、榎町工場・早稲田分工場・山吹寮・弁天寮等焼失、死者7人」と記されているが、それ以外は、ほとんど空襲被害を受けずにすんだ印刷工場だった。しかし、「四月、五月と何回かの空襲によって従業員の罹災者が多く出て欠勤者が増え、さらに一部の従業員は疎開していたため、生産能力は著しく減退した」。また、共同印刷、凸版印刷、大蔵省印刷局などが罹災し、「大手印刷会社で唯一、焼け残った当社の市谷工場には、大蔵省印刷局から作業員が派遣され、『官報』の印刷が行なわれた」(『大日本印刷百三十年史』)という。その一方で、1945年3月以降、仙台・福島・山形・秋田などへの工場疎開命令を受け、準備を進めてもいた。「そのころは機械も疎開していて、東京の工場では何分の一かになっていましたが、その機械のほとんどは、地図やデータなどを作るために軍に提供していました」(鈴木金蔵「私が歩んだ印刷人生」『大日本印刷百三十年史』に抜粋再録)という証言が残されているのだから、急速に、民間向けの余力がなくなっていたのだろう。
『青年読売』とほぼ同時期に休刊になった大日本飛行協会の『飛行日本』では、1945年3月号までの印刷所は大日本印刷だったが、休刊号とされる1945年4-5月合併号(1945年5月1日発行)からは、長野市南県町の信濃毎日新聞社印刷部となっている。この号の表紙は、本文と共紙という最も簡略な体裁になっていて、「編輯室より」に、長野市新田町103に編輯分室を設置したことが告知されている。
「★本誌もいよいよご覧のとほりの戦時版となつた。理由は資材その他の関係である。殊にグラビア印刷の進行が著しく遅れ、従来の形式を固執してゐては到底月刊の月刊たるの意義を保持出来ないからである。(中略)
★戦時版の形式を採用すると共に本誌は今般左記に編輯分室を設置することになつた。(中略)
★戦局はいよいよ切迫し、ますます重大化す。この秋に於ける吾々航空科学雑誌編輯者の任務は容易ならざるものである。本土の津々浦々が驕敵米B29の醜翼にさらされ、局部的にはあらゆる種類の敵機の来襲を見る。もはや「航空」の二字は完全に国民の生活に浸透し、「航空科学」の普遍と進歩こそはこの戦ひに勝つ因子であらねばならぬ。本誌が敢て戦時版を発行するのも、責任遂行のあらはれた結果の一つである。」



65回 『青年読売』の最終号は、1945年4月1日発行の「第4輯」(1)
時代は少し飛ぶが、1951(昭和26)年7月から1960(昭和35)年12月までの9年半の間、週刊誌の定価30円時代が続いた。
まず、1951年5月1日、新聞・出版用紙の統制が完全に撤廃される。18年後に刊行された『日本雑誌協会史 第二部』(日本雑誌協会、1969年)は、1951年の状況を以下のようにまとめている。
「紙の生産量はますます増大して、優に需要量を満たし得る状態になったため、用紙の割当統制は五月に廃止となり、新しい局面を迎えた。その後高値をつけていた紙価もようやく横這状態を経て値下りを始めた。
出版界はこの好機を購買力を高めるために活用し、雑誌出版の面では定価据置きのまま増頁の施策をすすめる出版社が多かった。
書籍出版の面では用紙の良質化、造本の改善などを行なって、読者サービスを心掛けたため、書籍の売行きもさらに上向き出版界の安定に好影響をもたらした。
この年の書籍・雑誌の出版量は前年比でみると、書籍の総冊数は一割増加、雑誌総発行部数も一割増を記録した。
政治的にも経済的にも、また業界の動向の面でもこの年は戦後における最初の転換の年となり、出版界も新しい時代への歩みを確実にすすめていた。」
雑誌の定価は据え置きのままでページ数が増え、発行部数も増えるとは、読者にも出版社にもうれしいことだ。実際に1951年当時の週刊誌――まだ『週刊サンケイ』は創刊前で、『週刊読売』は『月刊読売』という名前だった時代だ――を見ると、『週刊朝日』と『サンデー毎日』は両誌とも発行日が一緒で、1951年7月1日号から同時に定価30円になっている(4月から6月は定価25円、それ以前は定価20円)。定価だけではない。7月1日号のページ数はどちらも、表紙・裏表紙を合わせて56ページである。
のちに『週刊読売』に発展する『月刊読売』は、1951年4月から月2回刊(1日、15日刊)となっているが、このころの定価は、週刊誌と同じ30円である。

「本誌は昨年九月号から定価三十円の「時局娯楽雑誌」として新発足して以来、毎号増刷をつづけながら今日にいたりましたことは、愛読者各位のご支援によるものと深く感謝しております。
ご覧のように本号より建頁を増し、オフセット頁を含めて合計七十二頁の、絶対他誌の追従をゆるさぬ独特の企画を盛って各位のご愛顧に応えることといたしました。
けれども、内外の情勢、時局の変転、日をおつて眼まぐるしい昨今、本誌はその役割の重大さを痛感し、一層各位のご声援に応えるために、敢然、四月より一日号、十五日号の月二回の画期的発行を行います。
ザラ紙はマル公〔丸の中に公=公定価格〕の二倍、仙花紙は三割と暴騰して、業界多難が伝えられていますが、本誌は増ページ定価据置きのまま、更に本社のあらゆる新聞通信網を活用して、世界情勢、時局問題、生活、娯楽と…………一切の情報と話題を百パーセント提供して、各位のご期待に添いたいと思います。
この機会に愛読者各位の旧倍のご支援とご教示を切にお願いしてやみません。 月刊読売編集部」
なるほど、『日本雑誌協会史 第二部』が俯瞰してみせた構図はじつに的確で、1950年9月から定価30円だった『月刊読売』は、誌名はそのままで月2回刊に移行する直前の1951年3月号から、定価据え置きで増ページ(表紙・裏表紙を合わせて60~62ページであったのを、72ページに増やす)を敢行していたのである。


もっと残念なことは、この本の「解題」では、『月刊読売』から改題された『青年読売』が、1945(昭和20)年3月号(第3巻第3号)で終わったと、ほぼ断定していることだ。『月刊読売』と復題した戦後復刊号(1946年1月1日発行、第4巻第1号)の「巻頭言 新らしき出発」文中の「去る四月休刊の止むなきに至つて今日に及んでゐる」を、無理やり「4月号から休刊になったと解釈」しているのであるが、その根拠は、「現段階において第3巻第4号が刊行された痕跡はどこにもない」からだという。
そこで、私としては、最近入手した『青年読売』第3巻第4号(1945年4月1日発行)を紹介しなければならない。手元にある1945年1月号、2月号の表紙には、月号を示す「1」「2」があるが、第3巻第4号には「4」(月号)ではなく「4輯」と印刷されていることに注目してほしい。









